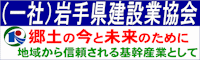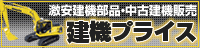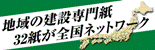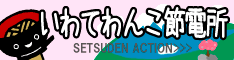コラム集
- ●つむじ風 7月26日
- 「地熱由来の電力を使えることをPRしていきたい」。全国で初めて地熱発電所の電源をメインとする地域新電力会社「㈱はちまんたいジオパワー」の設立に当たって、八幡平市の佐々木孝弘市長はこれからの展望を語った▼地域新電力会社は、松尾八幡平地熱発電所と安比地熱発電所を主な電力の調達先として、市内の民間20施設、公共58施設に対して電力を供給する予定。電気におけるCO2ゼロを実現するという環境価値を付加したゼロエミプランの提供も検討している▼市では、地熱由来の電力を企業誘致にもつなげたい考え。24時間一定の発電量がある地熱発電は他の再生可能エネルギーと比較して電気の質が良いことに加えて、社会的な環境意識の高まりなどを背景に、すでに関心を示している企業もあるとか▼環境面に配慮できる企業であることを、短期的な経済面でのメリット異常に重視する企業が増えているのかもしれない。23年のニューヨーク・タイムズ効果ではないが、外部から人や投資を呼び込むことができる地域資源は、県内にはまだ多いのでは。
- ●つむじ風 7月25日
- 県建設業協会青年部連絡協議会会長の木下伸一氏は、東北建設業青年会の会長に就任した。木下会長は建設専門紙の共同記者会見の中で、「東北は一つを合言葉に組織の強化を図っていく」と決意表明。東日本大震災の教訓の伝承・発信をはじめ、建設業の担い手の確保に向けたPRなど、6県の会員で結束する考えを示した▼広い県土を誇る岩手の社会資本整備は、道半ばだ。三陸沿岸道路などが出来上がったとはいえ、その他の道路や河川、砂防など防災上の課題を抱えている所は多い。市町村からの要望もインフラに関するものが大きなウエートを占める。東北全体を見渡しても、太平洋から日本海までを結ぶ強靱な道路の整備を求める声も大きい▼木下会長は「東北建設業青年会が地域のために何をなすべきか、真剣に考えなければならない」と強調。「公共事業不要論に対しては、理路整然と反論していく必要がある」と訴えた▼産業の基盤を支える建設業と各地域の発展は、表裏一体の関係にあるのでは。共通課題を克服しつつ、東北全体の盛り上がりを期待したい。
- ●つむじ風 7月23日
- 大船渡市と遠野市を結ぶ国道107号の整備促進、(仮称)大船渡内陸道路の高規格化を求める期成同盟会は、21日に初の決起大会を開催。地方から中央に向け、道路の必要性をアピールした▼大船渡市から釜石自動車道の宮守インターチェンジ間の国道107号は、重要港湾大船渡港と産業集積が進む内陸を結び、産業振興を支える上で重要な路線となっている。特に大船渡港は、コンテナ貨物取扱量が年々増加しており、昨年度は過去最高を更新。安定的な輸送を確保するため、さらなる道路ネットワークの強化が求められている▼大会では首長メッセージで、渕上清大船渡市長が「内陸の元気を道路を通して沿岸に運んでいただき、共に良くなることが県土の発展につながる」、多田一彦遠野市長は「子どもたちの将来の可能性を広げるためにも必要な道路」と語っていた▼国道107号は産業振興をはじめ、救急搬送、観光ルート、災害時の輸送など重要な役割を担っている。地域の未来を支える横断軸として、整備促進と予算確保を訴えていく必要があるだろう。
- ●つむじ風 7月22日
- 肴町商店街に11日、複合商業施設「mоnaka」がオープンした。肴町商店街にあれだけの人を見たのは何年ぶりだろうか。直後の3連休にも、多くの人が詰め掛けていた▼「盛岡らしさの真ん中」との意味も込められている「mоnaka」。その名の通り、河南地区は藩政時代から「商業・文化の中心地」として栄えてきた。川徳デパートの移転後、残った施設は中三、Nanakと変遷。施設の老朽化もあり、5年前から空き店舗となっていた▼長らく「地盤沈下」が懸念されていた河南地区だが、22年10月に新盛岡バスセンターが開業した。今回、mоnakaのグランドオープンに訪れた多くの人々の心の中には、河南地区活性化への期待が込められていることだろう▼現代の「盛岡の城」とも言うべき県庁と盛岡市役所。ともに老朽化が著しく、改善に向けた検討が進められている。市役所については、市の審議会が移転場所として「内丸エリア」を選定し、近く基本構想案を答申する予定だ。今後のまちづくりを左右するものだけに、市の判断が待たれる。
- ●つむじ風 7月19日
- 一時期、県議会での当局の答弁で「適切な手続きを経て実施しています」という主旨の発言が気になったことがある。議会側が結果とそれに対する見解を質したことに対して、プロセスと手続きで答えるのだから、噛み合うはずがない▼以前は業界と行政との意見交換でも、これに近いやりとりがあったことを覚えている関係者も多いだろう。入札制度で業界が重視するのは「その施策を講じたことで、業界にどのような影響が生じるのか」。それに対する回答を聞く限り、行政サイドが重視しているのは「行政プロセスをいかに適切に執行するか」ということのようだ。やはり噛み合うはずがない▼今ではある程度同じ方向を見ながらの議論に変化しているように見える。08年の岩手宮城内陸地震から続く、一連の災害対応への信頼がその土台にあるのかもしれない。それでも繰り返し言いたいのは「災害があったから建設業が必要になったのではない」ということ。先ごろ始まった建設業地域懇談会でも、同じ方向を見据えて噛み合った議論が行われることが望まれる。
- ●つむじ風 7月18日
- 県土整備部が県の構想路線の一つとして検討を進める(仮称)久慈内陸道路。先の県議会6月定例会では、検討を優先する葛巻町内の区間で、ルート検討の精度を上げていくとの方針を示した▼盛岡市から国道281号を経由し、葛巻町・久慈市方面に向かうと、峠道の急カーブなど課題となる箇所が多い。一方で、改良整備が着実に進められてきたことも実感する▼6月定例会の一般質問では、県議会議員から「地元で決起大会が開かれるなど、地域住民の思いが強い路線」との声が上がり、盛岡以北の横断道路の整備を訴えていた。県側は、沿線市町村と丁寧に意見交換しつつ、より詳細な地形図などを用いてルートを検討していく考えを示した▼6月の北岩手・北三陸横断道路整備促進期成同盟会による決起大会では、東北地方整備局の講演があり、食料分野を東北の強みの一つとして打ち出していた。地場産品の販路拡大、食料基地の強化という視点でも、道路が果たす役割は大きい。地場産業などを強く下支えするよう、県北の大動脈の道路を検討してほしい。
- ●つむじ風 7月17日
- 最近、幼稚園児や小学校低学年の児童らを取材する機会があった。建設業の仕事や役割を知ってもらおうなどと企画したもので、中には保護者も参加していた▼楽しそうに見学する園児や児童ら。文章で雰囲気を伝えることができないのがもどかしいが、いきいきとした表情が全てを表していた。楽しそうな雰囲気とは裏腹に、現場の緊張感も伝わってくる。急に走り出したりしないか、動いている重機に近づこうとしないか…▼重機を試乗した際、ある男の子がとても楽しそうにしていた。その様子から察するに常日頃から、やんちゃな行動をとるのかなと思っていた。すると先生が、「珍しい。こんな様子は見たことがない」ととても驚いていた。聞くと、普段は大人しく、物静かな男の子という▼園児らに作業しているお兄さんの感想を聞くと、「かっこいい」と即答。企画する側の大変さはあるが、園児らの笑顔や質問コーナーで多くの手が挙がる様子を見ると、大変さが吹き飛ぶのではないだろうか。これからも未来の担い手に建設業の魅力を伝え続けてほしい。
- ●つむじ風 7月13日
- 県建設業協会千厩支部青年部会では、管内を走る国道284号、343号の道路清掃を長年続けている。両路線に特化した清掃に関しては09年度から始め、地元住民をはじめ観光などで路線を利用するドライバーらに快適に走行してもらおうとの思いに加えて、11年度以降は県が路線を復興支援道路に位置付けたことから、沿岸の復興への願いといった思いも込められている▼復興支援道路に位置付けられるなど、両路線は管内でも重要路線。国道284号では室根、真滝バイパスなどの整備が着実に進められてきたほか、一関市千厩町境地区では概略設計が計画されている。国道343号については、地元などから同市大東町と陸前高田市の間に位置する笹ノ田峠へのトンネル整備が悲願となっている▼道路の環境整備に取り組む様子を、清掃を始めた当時から取材し続けてきたが、取材するたびに交通量の多さ、急勾配や急カーブが感じられる箇所などを肌身に感じている。道路に対する思いを込めた活動が、必要箇所の改良などにもつながっていくことが期待される。
- ●つむじ風 7月12日
- 県土整備部の広報媒体として毎月のタイムリーな話題を提供している「美しい県土づくりNEWS」。今年8月で創刊20周年を迎えるとのこと。県のホームページには「復刻版」として、過去に発行した分を更新、掲載している。7月11日現在、12年4月号までが復刻した▼当時の職員の顔ぶれにしみじみし、「達増知事は変わらず若々しいなぁ…」など本筋でない部分に時間を取りつつ、24年度は上半期から、南三陸事務所の開所、災害公営住宅の第一弾着工、復旧・復興ロードマップの策定、大船渡湾口防波堤の災害復旧に着工、高田地区海岸災害復旧工事に着工など、東日本大震災から1年余りでこれだけの動きがあったのかと、今さらながら驚かされる▼当時は未だ被災の傷が癒えない中であったが、「より良い復興」に向けた力強い槌音の響きが感じられる。これらは同時に、地場企業をはじめとする建設産業が復旧・復興に果たしてきた足跡でもある。建設産業の社会的な意義を一般に理解してもらうためにも、復刻版が多くの県民の目に止まることを願いたい。
- ●つむじ風 7月11日
- 9日に開かれた県土整備部と県出納局、県建設業協会(向井田岳会長)との意見交換会では、洋野町内で発生した豚熱の防疫対応が話題に。建協側は、県土整備部などの広報により、新聞・テレビで協会員の防疫対応が取り上げられたことに謝意を示した▼向井田会長は「われわれの活動を記者クラブに発表していただき、テレビや新聞、一般のマスコミで取り上げていただいた。本当にありがたい」と述べた。その上で「建設業の取り組みを、決して誇張するのではなく、当たり前に実施していることを紹介していただくことが重要だ」と話した▼現地で対応した岩瀬張敏行久慈支部長は、「ニュースの後、一般の皆さんからも『大変でしたね』と声掛けをいただいた」と喜びを語った。建協では、県の土木サイドや家畜保健衛生所と今回の課題・教訓を共有し、今後の備えにつなげるという▼地域建設業者は、一般の皆さんの目の届かないところでも、汗を流して県土を支えている。地域が存続するためにも不可欠な業界であることを、さまざまな場面で訴え続けたい。
- ●つむじ風 7月10日
- 1875年に観測業務を始めて以来、2025年で150年の節目を迎える気象庁。子ども達の世代が自然災害について学び、深く考えてもらう契機となることを期待して防災展示アイデアコンクールを企画。応募資格は、国内の小中学生となっている▼アイデアを作成する際に、三つの段階を踏むことをポイントとして挙げている。▽伝えたいテーマを勉強しよう▽伝え方を考えよう▽見せ方を考えよう―とアドバイス。何についての仕組みを示すアイデアなのか分かるようなタイトルを付けるようにとも▼先日開かれたEE東北24。各出展ブースの間口は3㍍、奥行きは3㍍、高さ2・4㍍。基本仕様は同じはずなのに、創意工夫が凝縮された各ブースの空間は、それぞれが別世界のようだった。改めて、人に伝えるための見せ方・見え方の重要性を考えさせられた▼小中学生からどのような防災展示のアイデアが出てくるのか今から楽しみだ。建設業界を人に伝える際にも、アイデアを作成する際のポイントに学び、見せ方・見え方とともに、魅せ方についても考えたい。
- ●つむじ風 7月9日
- 県が住田町内を流れる気仙川で、架け替え事業を進める昭和橋。同橋は現在、下部工を推進中。今秋には上部工の公告も予定されており、26年3月の供用開始を目指し事業の進捗が図られていく▼整備場所は、同町世田米地内。町役場周辺の町中心部で、新橋の規模は橋長が72㍍、全体幅員7・8㍍。「1車線+2歩道」の、2径間連続プレビーム合成桁橋で整備される。事業は、旧橋の橋脚の間隔が狭く、川底から橋桁までの高さも不足していたため、増水時に流木などが川の流れを妨げる恐れがあることから計画された▼県は宮古市内の花輪橋でも、架け替えに向けた取り組みを推進。先月下旬に詳細設計の担当業者が決まり、今後は上・下部工の設計などが進められていく。閉伊川に架かる花輪橋も昭和橋同様、橋脚の間隔が狭いため、増水時に流木などが川の流れを妨げることなどが懸念されていた▼気候変動に伴い、雨の降り方が変化している中で、豪雨災害の激甚化・頻発化も危惧されている。橋梁の架け替えなどを着実に展開し、災害に備えていきたい。
- ●つむじ風 7月8日
- 一関市は、市営建設工事を巡る官製談合を受け、入札制度等改革本部会議を設置。職員の法令遵守の確立、これまでの入札事務の検証を行い、不正入札の再発防止策を検討し、立案する構えでいる。佐藤善仁市長を本部長に、副市長や教育長、市の部長級職員のほか、外部委員として国交省や県の職員、建設関連業界団体、弁護士などからの意見聴取も想定している▼各市町村議会などで、入札制度に関する一般質問を聞く機会もあるが、落札率の高さから改革の必要性を指摘するのには、業界に造詣のある多くの人は首を捻るのではないか。業界の実情は、どの程度理解されているのだろう▼業界紙の場で改めて論じるまでもないが、業界団体では技術と経営に優れた企業を掲げて活動し、多くの建設業者は高い積算能力を有する。業界側は長年、実勢単価と設計単価がかい離している状況を、さまざまな場で訴え続けてもいる▼落札率の高いことが、イコール不自然という風潮にだけはなってほしくない。今週からは、地域課題を話し合う建設業地域懇談会が始まる。
- ●つむじ風 7月5日
- 建設業は社会資本の整備と維持管理に携わる仕事であり、時には休日返上で働くこともある。これは良い悪いではなく、あくまでも仕事の特性。朝早くから始まる仕事もあれば、屋内で終日座りっぱなしの仕事だってある▼県電業協会は、会員企業を対象に23年の働き方の現状調査を行った。技術職の週平均労働時間は40~41時間、技能職は37~39時間程度。週平均の時間外労働時間は技術職・技能職ともに4~6時間程度、月平均の休日労働時間は技術職・技能職ともに2~4日間だった。停電作業など休日業務はあるが、可能な限り振替休日や代休で対応していることが見て取れる▼同協会は若年労働者の確保に向けて、テレビCMを放映。「ハイクオリティを目指す技術集団」である県内電気工事業の社会的な存在意義をPRしている。停電作業が付きものの電気工事業は、人が休んでいる時こそ必要とされる仕事。そんな中でも休日は確保されている。ライフラインに携わる、大変だが誇りと責任ある仕事の価値が伝われば、この道を志す若い人も増えるのでは。
- ●つむじ風 7月4日
- 7月には、県と建設業界との意見交換が予定されている。今年も、県内各地区を巡る建設業地域懇談会のシーズンを迎えた▼県議会の商工建設委員会では、出席委員から「建設業界は、県民生活の基盤を支えている。意見交換の中で、地域単位の課題をしっかりと把握してもらいたい」との声が上がっていた▼さらには、親身になって現場の声を聞く姿勢を大事にし、「業界側が即効性を求める要望」と、「長期的に改善を求める要望」などを丁寧に整理することも求めていた。その委員は「広い県土を守る原点は、県土整備部にある」とも▼社会資本の整備・維持管理や、激甚化・頻発化する自然災害への備え、豚熱や鳥インフルエンザに対する防疫措置など、幅広い視点からも、岩手には地域建設業の力が不可欠だ。地域を担う建設産業の発展のためにも、県と業界との間で現場の課題を洗い出したい。一朝一夕で解決できるものばかりではないことは承知しているが、円滑な施工に向けた現場の声、豚熱対応の教訓など、制度設計に生かせるものも多いはずだ。
- ●つむじ風 7月3日
- 文部科学省と国土交通省、警察庁は、全国の市町村立小学校の通学路で合同点検を実施し、3月末時点の取り組み状況をまとめた。全体数7万6404カ所のうち、対策済みは7万2160カ所だが、暫定的な安全対策を含むと全箇所が対策済みとなった▼本県の全体数は908カ所。暫定的な安全対策を含めると100%だが、対策済みは822カ所で9割。実施機関別で見ると、教育委員会・学校は519件で全て対策済みだ▼警察は171カ所のうち対策済みは170カ所。一方、道路管理者は388カ所のうち対策済みは312カ所で、8割にとどまっている。警察が実施する対策は、信号機の設置や速度規制の実施など。道路管理者は、歩道の設置・拡充や防護柵などの整備が挙げられている▼通学路の合同点検に至ったのは、千葉県八街市で小学校の児童が下校中に飲酒運転のトンネルにはねられ、5人が死傷した事故がある。あれから3年が過ぎた。通学路の安全確保に向け継続的な点検や改善はもちろんだが、ハンドルを握る重みや心構えを再認識したい。
- ●つむじ風 7月2日
- 1日から始まった全国安全週間を前に、大船渡市内で開かれた建設業労働災害防止気仙地区大会。当日の安全講話では、大船渡労働基準監督署の西村浩二署長が熱中症対策について説明していた▼西村署長は昨年県内の職場で発生した熱中症について、全体の3割が屋内での作業中であったことを指摘。屋内だからといって油断してはならないことを強調した。発生した時間帯は多くが午前中であったこと、熱中症になった年代は20歳代が最も多かったことも示し、「意外に感じる人も多いのでは」と話していた▼さらに熱中症で死亡した事例から、部下が体調不良を申し入れてきた際の注意点も説明。初期症状は、風邪をひいた時と似ていて、判断ミスを起こしやすいこと。熱中症の症状が急速に悪化し死亡するケースが多いため、一人で休憩させず、すぐに救急車を呼ぶよう訴えていた▼「熱中症は、上司の判断次第で部下の生死が分かれる」とも。夏本番を前に今一度熱中症についての知識を再確認し、休憩設備を整えるなどの対策をしておく必要があるだろう。
- ●つむじ風 7月1日
- 県建設業協会青年部連絡協議会による各地区での建設業ふれあい事業が始まっている。事業は回数を重ね、先日取材した地区では、1回目に催した学校での事業となったのことで、当時を知る部会員は懐かしんでいる様子だった▼次代を担う子どもたちが建設業に理解を深め、建設業を志望する子が増えればとの思いを込めた事業では、回数を重ねる中、ふれあい事業を一つのきっかけに建設業へ進んだ人たちもいると聞く。着実に成果が出ている表れだろう▼事業では、子どもたちの体験中にも部会員らが綿密に打ち合わせをするとともに、「この点を改善して次回はやろう」などと話し合っている場面を見た。長年取り組んできたものだが、よりスムーズに進行し、安全に体験を楽しみ、建設業の魅力をさらに伝えるため、各会員が事業に真剣に向き合っているのを感じられた▼事業後には、反省会のようなものでさらに深く議論を重ねていることだろう。こうした姿勢によって事業が長く続き、子どもたちが安心して体験を楽しみ、建設業への理解を深められている。
- ●つむじ風 6月28日
- 文庫化が大きなニュースになるのは珍しい。ガブリエル・ガルシア=マルケス『百年の孤独』の文庫版が26日に新潮社から出版された。発売前から事前重版が決まるほどの売れ行きだという▼名著として名高く、多くの著名人が愛読書として挙げる『百年の孤独』。一言で表現すれば「マコンド」という架空の町を舞台にしたブエンディア一族の物語というところか。何代にもわたって同じ名前の登場人物が繰り返し出てくることや、ファンタジーと現実を行ったり来たりするような展開に翻弄され、挫折した人も多いらしい。あるいは読了こそしたが断片しか頭に入っていないという人も▼繊細な金細工職人から革命軍のリーダーになったアウレリャノ・ブエンディア大佐、一族の精神的な支えとも言える初代のお母さんウルスラなど魅力ある登場人物は多いが、才気に富み町を開拓しながらも晩年に心を病むホセ・アルカディオ・ブエンディアに、創業者の孤独を読み取る経営者もいそうだ。かつて挫折したという人も、文庫化をきっかけに改めて手に取ってみては。
- ●つむじ風 6月27日
- 洋野町で発生した豚熱の防疫措置に尽力してきた県建設業協会久慈支部(岩瀬張敏行支部長)の会員企業。19日には、達増拓也県知事が久慈建設会館を訪れ、会員らに対し謝意を示した。支部会員らは、埋却溝の整備やフレコンバッグの運搬などに従事。支部会員39社が総力を結集し、24時間体制で現場作業に当たった▼岩瀬張支部長は「掘削場所によっては、水が出るといった課題があった。試掘調査など、事前の備えが重要だ」と課題を整理。各地域における支部の体制維持の重要性も指摘していた▼達増知事は「今回の対応を好事例として、他の地域の参考にしていく」とし、「地域の担い手を確保するためにも、建設業がいかに地域のために貢献しているのかを、県からも発信しなければならない」との認識を示した▼支部会員によると、重量200㌔を超えるような母豚などを運搬したりする必要があり、重機の追加配備などの対応も必要だったという。現場の機転や組織力が発揮された一例と言えるだろう。建設産業は、やはり地域になくてはならない。
- ●つむじ風 6月26日
- 2012年5月の茨城県等で発生した竜巻をきっかけに開催した「竜巻等突風の強さの評定に関する検討会」。気象庁はこのほど、同検討会の報告書を取りまとめ公表した▼同検討会では、風工学や気象学の専門家、気象庁が連携して、日本の建築物等に対応した日本版改良藤田スケールに関するガイドラインを策定。ガイドラインの科学的な妥当性を評価するなどの検討の過程などを今回報告している▼昨年4月、本県内陸部を中心に強風が吹き荒れた。北上市での取材後、道路にトタン屋根らしき物体が覆いかぶさっている現場に遭遇した。後に報道で、車が下敷きになっていることを知った。けが人はなかったものの、車ではなく人だったら…と考えてしまう▼突風が発生した時の気圧配置は台風、気圧の谷、雷雨(熱雷)、寒気の移流が多く、個々の被害では木造住宅と園芸施設、木造非住家、広葉樹が多いという。過去の検討会では、16年以降に年別の突風発生確認数は減少しているとの見方も出されていたが、発生しやすい気圧配置などを参考にしながら備えたい。
- ●つむじ風 6月25日
- 東北地方整備局三陸国道事務所は、山田町内に位置する三陸沿岸道路・山田北インターチェンジ(IC)のフル化を計画。20日付で工事の第1弾を公告し、着工に向けた準備を進めていく▼事業は、国道45号の防災上のあい路を回避するため、同ICに北向きの乗り降りを整備し、災害時の道路ネットワーク機能を確保するもの。今回の整備箇所は、同町石峠第3地割。山側に新設するランプの本線合流部分で、道路土工、地盤改良工、擁壁工を施す予定となっている▼管内の三陸沿岸道路では、宮古市内の津軽石パーキングエリア(PA)に、トイレ棟の新築も計画されている。PAへのトイレ設置は県内では初。事業は津軽石PAの上下線に各1棟、木造平屋建ての床面積37・54平方㍍のトイレを設置するもの。工事は5月末に公告され、7月の開札を控える▼21年12月の全線開通後、地域振興を後押ししている三陸沿岸道路。さらなる利便性の向上、沿線住民の安全安心な暮らしを支える取り組みを進めることで、沿岸部の縦軸幹線としての機能を高めてほしいと思う。
- ●つむじ風 6月24日
- 先週の県内は、季節を先取りしたような暑さが続き、30度を超える真夏日に見舞われた日もあった。まだ、身体が暑さに慣れていない時期などとして、熱中症への注意がさまざまな場面で呼び掛けられている▼個人的にここ数週間は、道路清掃や草刈り、施工現場、建設業の体験学習など野外で取材する機会に多く恵まれ、日差しの強さや暑さを肌身で感じている。周囲は建設業従事者とあって、熱中症対策をしっかり講じている印象を持ちながら取材していた▼さまざまな熱中症対策があるが近年、空調服を着用する従事者が目立つようになり、業界では定着してきているように感じる。ここ数週取材した野外でのイベント、移動中などにも施工現場で交通誘導員や作業員らが着用しているのをよく見かける。暑さが厳しい昨今、さらなる熱中症対策に関するアイテムが出てくることにも期待がかかる▼季節先取りの暑さが続いたが、梅雨入りすれば今度は梅雨寒や長雨に見舞われる日が続くことも予想される。一層、体調面には気を配って日々の業務に励んでいきたい。
- ●つむじ風 6月21日
- 社会資本整備の上流部に当たる建設関連業務。それは同時に、公共事業の減少局面では真っ先に影響を受けることを意味する。東日本大震災からの復興工事が最盛期を迎えていた段階から、事業量の急激な減少を訴える声が挙がっていた▼県建設関連業団体連合会はこのほど、県内企業への積極的発注拡大や公共事業予算の確保などを県に対して要望。この中では、チャレンジ型入札制度や同一企業の重複落札への対策など、受注の偏在を防ぐための入札制度の見直しも提言した。県側も受注実績の少ない企業の受注拡大に対する一定の理解を見せ、業界との意見交換を積極的に行っていく意向を示した▼設計業務の成果品の精度向上は、施工者の立場からも重要な課題。現地にあった設計図書による入札が行われれば、契約後の円滑な着工につながる。元請けにとってプラスが多ければ、下請けや資材業者に対する好影響も期待できる。建設関連業における入札制度の改善は、川上から川下まで幅広い影響を与えるテーマであることを、行政当局は理解する必要がある。
- ●つむじ風 6月20日
- 先ごろ、決起大会を開いた北岩手・北三陸横断道路整備促進期成同盟会(会長・鈴木重男葛巻町長)。関係市町村の代表者や、国・県などの来賓ら約90人が出席した。大会では、県北部を横断する広域道路ネットワークの早期整備・着工などを関係機関に求める決議を採択した▼鈴木会長は「北・北道路を何とか実現したい」と強い思いを語った。達増拓也知事は来賓祝辞の中で、(仮称)久慈内陸道路に触れ、「今年度は、現道課題が多く確認された葛巻町内において、より詳細な地形図を用いて調査を進めるなど、一層調査を推進する」との考えを示した▼同盟会の大会決議では、「北岩手・北三陸を横断する広域道路ネットワークについて、早期に広域移動を支える基幹道路として整備・着工されること」などを採択。今後は関係機関に対し、力強く要望を実施していく▼広大な県土を誇る岩手において、道路は骨格とも言える重要なインフラ。特に県北地域では、道路網の脆弱性が指摘されることも多い。道路の必要性を整理して国などに訴え、整備の具現化につなげたい。
- ●つむじ風 6月19日
- 高速道路の4車線化事業を進めるNEXCO東日本。4車線化事業が気候変動への適応事業(グリーンプロジェクト)に該当するとして、㈱格付投資情報センターからサステナビリティ・ファイナンスに関する第三者評価を取得したと発表した▼同ファイナンスは、社会的・環境的課題を解決する事業に充当することを目的とした資金調達手段。秋田自動車道の北上西インターチェンジ(IC)から湯田IC間が対象区間となっており、大雪時のネットワーク代替性確保を目指す▼北上西ICから湯田ICの延長は約19・5㌔、事業費は約980億円を見込む。現道には7トンネルと11橋梁あり、延長が長いトンネルが多いのが特徴で、橋長100㍍以上が7橋ある。新たな車線でも同数のトンネルと橋梁の整備が見込まれている▼24年度から進入路など土工工事に入り、25年度からはトンネル工事を予定。26年度には土工工事やトンネル工事を継続するとともに、橋梁下部工にも入る見通しだ。調達した資金などを活用し、着実な工事推進と一日も早い4車線化が望まれる。
- ●つむじ風 6月18日
- 災害の歴史、経験を後世に伝えていくため、災害資料伝承館の新設を計画する宮古市。施設は建築工事の入札が終了。現在は設備工事2件が公告中で、25年7月の開設を目指し事業の進捗が図られていく▼施設は、同市田老地区の旧田老総合事務所跡地に整備。規模は、鉄骨造平屋建ての床面積462・04平方㍍で、内部には展示室や多目的室などを設置。津波、台風などの災害の歴史をテーマに、災害年表や体験者の証言映像、災害の痕跡を残す実物などの展示が想定されている▼大槌町でも震災津波伝承事業の一環として、同町須賀町地内に、町全体の追悼・鎮魂の場となる(仮称)鎮魂の森の新設を計画。整備工事は全ての入札を終え、今後は園路やメインエントランス、植栽、芳名碑・献花台の設置などが進められていく。全体完成は25年7月の予定だ▼災害による犠牲者を二度と出さないためにも、被災の経験と教訓を次世代へ伝承していかなくてはならない。2市町の施設とも、次の災害に備え命を守る取り組みについて考えることのできる場になればと思う。
- ●つむじ風 6月17日
- 小学生の我が子は近ごろ、格闘技を習いたいと話してくる。聞けば、放課後児童クラブに置いてある漫画に夢中になっているようで、その漫画の主人公などに魅力を感じている様子。子どもたちにとって、漫画の影響力の大きさを改めて感じさせられる▼県建設業協会が発刊した「我らイワケン株式会社」のように、次代を担う子どもたち向けに漫画を制作する業界は多いようだ。業界への理解を深めるとともに、興味を持つ子が増えてくれればと思う▼漫画では、週刊誌などで建設業について描いた作品を見たこともあるが、おおむね高校生以上を読者層と位置付ける青年誌に掲載されるケースが多い印象はある。憧れのような気持ちを抱いてもらうには、中学生以下にも見てもらえるような環境が必要にも感じる▼少年誌でも、建設業に関わりがあるものを題材にした作品が連載された事例はある。中には、著名な漫画家が描いた作品もあるものの、いわゆるヒット作になるまでは至らなかったようだ。子どもたちのブームになるような作品が生まれてくれないものか。
- ●つむじ風 6月14日
- 建設業界紙の記者職にありながら何だが、理系科目はことごとく苦手だ。これは中学2年生からなので、ちょっとやそっとではない筋金入り。「自然科学の単位が足りない!…あ、夢か」と、未だに大学時代の悪夢に魘されることも▼バーツラフ・シュミル『Invention and Innovation』(河出書房新社)が読まれているそうだ。「歴史に学ぶ『未来』のつくり方」の副題からして期待させる。すでに読了した方も多いだろう▼内容は「歓迎されていたのに、迷惑な存在になった発明」「主流となるはずだったのに、当てがはずれた発明」「待ちわびているのに、いまだに実現されない発明」等々…。翻訳も平易で読みやすいが、もう少し理系の素養があれば、さらに面白く読みこなせただろうに…。詳細は各自ご確認を▼読み進めながら、ふと思った。これって建設業振興施策も同じじゃないか。革命的な魔法の杖を期待するのではなく、歴史から学び、信頼の置ける手法を着実に進めていくことこそ必要。これは根っからの文系人間にも分かる。
- ●つむじ風 6月13日
- 東北建設業協会連合会(千葉嘉春会長)が先日開いた24年度通常総会では、東北地方整備局の山本巧局長による講演が行われた。東北地方のインフラと地域建設業という視点から、重要な論点が示されたように思う▼山本局長は「『人口が減っている中、これ以上インフラが必要ないのではないか』という主張もあるが、本当にそうなのか」と問題提起。「道路ネットワークなどが整備されてきたことにより、東北は成長してきた」と訴えた。東北地方の幹線道路ネットワークの変化を示しながら、東北が関東方面などへ農産物を出荷したり、企業立地の進展により半導体や自動車関連のサプライチェーンの一部を担ったりしていることを紹介した▼山本局長は「地域建設業は警察や消防と同じく、地域になくてはならない産業」と強調。継続的な国土強靱化の重要性も説いた▼東北建設業協会連合会や東北6県の各建設業協会では、「東北は一つ」を合言葉に、公共事業予算の確保などを進める。24年度も地域建設業の意義、社会資本整備の重要性を強く打ち出したい。