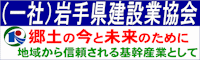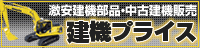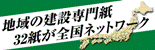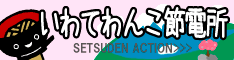コラム集
- ●つむじ風 4月3日
- 1日に開かれた政府の国土強靱化推進本部では、第1次国土強靱化実施中期計画の素案が示された。素案は、内閣官房国土強靱化推進室のホームページでも公開されている▼素案を見ると、計画期間は26年度から30年度までの5年間。事業規模は「今後5年間でおおむね20兆円強程度を目途とし、今後の資材価格・人件費高騰等の影響については予算編成過程で適切に反映する」としている。主要施策に関しては、「防災インフラの整備・管理」「ライフラインの強靱化」「デジタル等新技術の活用」「官民連携強化」「地域防災力の強化」の視点で整理している▼県建設業協会(向井田岳会長)は25年度を重要な年度と捉え、社会インフラ予算の確保と国土強靱化の計画的な推進などのため、関係機関に積極的な要望活動を展開する方針を示している▼県内の建設業は、東日本大震災や16年台風10号など、行政と連携しながら各種対応に当たってきた。強靱化を強力に推進すべく、技術的知見を持つプロフェッショナルとして、幅広い視点での提案や地域の声を大事にしたい。
- ●つむじ風 4月2日
- 国土交通省は、上下水道施設のメンテナンスの高度化・効率化に向けて、デジタル技術をまとめた「上下水道DX技術カタログ」を策定。同省ウエブサイトに公開した▼サイト内は対象施設と目的、要素技術に分類。目的は点検調査、劣化予測、施設情報の管理・活用、その他に分かれている。要素となる技術は、AI、ドローン、TVカメラ、ビッグデータ解析、ロボットなど▼水道が78技術、下水道は91技術で、下水道管路の「全国特別重点調査」に活用できる技術も掲載。導入自治体からのコメントやコスト、導入実績など利用者が知りたい技術情報も載せている。要素技術のAIでは、以前取材した水道管の老朽度を評価する手法や、工事費・管路延長を考慮し工事区間(グループ)を自動作成する手法が名を連ねていた▼国交省は、今後も定期的にカタログに掲載する技術を追加し、内容を充実していく考え。カタログを活用し、全国の上下水道で今後3年程度でDX技術を標準実装できるよう取り組みを実施していくという。当たり前を支える技術に注目したい。
- ●つむじ風 4月1日
- インフラそのものを観光対象として巡るインフラツーリズム。迫力ある景観や整備効果などを見て学べる観光として注目される中、三陸沿岸の防災施設も活用してもらい役割を情報発信していこうと、県は県立大学と共同でデジタルコンテンツを作成した▼コンテンツは、津波対策として宮古市内で整備中の閉伊川水門と、岩泉町の洪水対策として22年度に完成した小本川流木捕捉工を対象に制作。完成後の水門の開閉動作や、洪水時に河川で流木を捕捉する様子が、CGによって映像化されている▼水門の映像はAR(拡張現実)技術により、スマートフォンで現場の景色に投影し見ることができる。水門現場には、これまでも多くの見学者が視察に訪れており、今後は作成されたARを体験することで、津波がまちを守るイメージをより実感しやすくなるだろう▼新年度に入り、震災学習や教育旅行を企画・検討する学校などもあるはず。構造物の役割や必要性を分かりやすく伝えるコンテンツが、土木への理解醸成、さらに将来の職業選択にもつながればと思う。
- ●つむじ風 3月31日
- 建設業の魅力に、造ったものが地図に残ることや人のための仕事を実感しやすいことなどが、たびたび挙げられる。建設業の大きな魅力だが、魅力は逆に大変そうと思われる要素にもなり得る▼個々に趣味嗜好は異なり、Z世代などと次代を担う若手について一括りにするのは良くないかもしれないが、傾向を捉えることは担い手確保、建設業で長く働いてもらうために必要なことだろう。明日から新年度となるが、新たに建設業へ入職してくる社員らが定着し、スキルを着実に身に付け、次代を担っていく人員となっていくべく大事に育てていきたい▼新入社員に加えて、異動などで環境が大きく変わる時期ともなる。建設業においては、新入社員や新たに業務に就く社員に対して、最初の段階の時期にこそ、十分な安全衛生教育をして、安全や健康第一を身に付けさせることが大切に思う▼県内では、今年に入って労働災害が多発傾向にある。新年度を無災害で過ごすためにも、安全教育を徹底したい。労働災害は、経験期間の浅い人員に多いことが特徴でもある。
- ●つむじ風 3月28日
- 県は25年度、次期水道ビジョンの策定に着手する。「持続」「安全」「強靱」を三つの柱に現状と課題を分析し、将来目標と実現方策を設定。広域化や老朽化対策、技術の継承などについても議論が進むものとみられる▼滝沢市の水道給水開始から50年を記念した講演会が先ごろ催された。パネルディスカッションでは、同市の水道の未来について意見交換。パネリストの一人から「当たり前という言葉は好きでないが、その当たり前を支える人の存在が伝わっていない」との重い言葉があった▼別のパネリストは「当たり前の反対語は『ありがたい』。これは『有ることが難しい』ということ」と話し、水道施設の必要性に関するコミュニケーションの大切さも説いていた▼本来は「有り難い」ものである水道施設を当たり前に維持していくため、水道に関わる人や技術の持続可能性を、県の次期ビジョンの中でも問い直していく必要がある。そういえばいつの間にか「エッセンシャルワーカー」という言葉も聞かれなくなった。両方の意味で「ありがたい」仕事なのに。
- ●つむじ風 3月27日
- 県土整備部港湾空港課がまとめた久慈港長期構想の素案。長期構想は、同港を取り巻く環境の変化などを踏まえ、おおむね20年から30年先を見据えた将来像を示すものとなっている▼長期構想の基本目標は、「暮らし・エネルギー・地域産業を守り育む県北の拠点港『久慈港』」。構想では「物流・産業」「環境」「賑わい・交流」「安全・安心」の分野で、施策を整理している▼物流・産業分野では、物流のニーズに合ったふ頭の再編や、エネルギー産業拠点の形成などに取り組む。環境分野では、藻場の造成などを推進。賑わい・交流分野では、クルーズ船の受け入れ機能の強化や、新たな静穏海域を活用したレクリエーション機能の充実などを目指す▼安全・安心の分野では、港湾施設の計画的な点検や補修を実施。湾口防波堤や耐震強化岸壁の整備などを進め、広域的な緊急物資ネットワークを形成する▼取り組みの着実な進展に伴い、同港から周辺地域への波及効果も期待されるだろう。県北部のポテンシャルをより引き出すため、今後の取り組みに注目したい。
- ●つむじ風 3月25日
- 山田町では同町船越の産直ひろば「ふれあいパーク山田」(旧道の駅「やまだ」)が、1月末に道の駅「ふなこし」として再登録された。施設は改修工事が進められており、7月の全面リニューアルが予定されている▼改修工事は、建設から23年が経過し老朽化が著しいため、時代のニーズに合った施設に整備するもの。休憩所とトイレの間では現在、情報提供施設やベビールーム、屋上に展望テラスを備える建物(鉄骨造平屋建て、床面積104・68平方㍍)の新築工事が推進中。屋根付き通路なども設置される計画になっている▼町内では23年7月に、三陸沿岸道路・山田インターチェンジ付近で道の駅「やまだ」(愛称記おいすた)が移転・開業。昨年9月には累計の来場者で100万人を達成し、多くの観光客などに利用されている▼今回の登録によって二つの道の駅を有することになった町は、共にゲートウェイとして相乗効果を図り、経済の活性化、交流人口の拡大などにつなげていく方針だ。施設の特色を生かしつつ、山田の魅力を発信してほしいと思う。
- ●つむじ風 3月24日
- 埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け、国から自治体に「下水道管路の全国特別重点調査」の実施が要請され、今後調査が進められる。八潮市での事故以降、下水道管路の老朽化が注目されているが、こうした衝撃的な事故を受け注目されるケースは多くある▼インフラ施設では、12年の中央自動車道(上り)笹子トンネルの天井板落下事故を頭に浮かべる読者が、やはり多いだろうか。笹子トンネルの事故は、道路インフラメンテナンスの考え方を大きく変える転機となり、道路構造物の5年に1度の点検が定められた▼下水道管についても、5年に1回以上の点検が義務付けられている。八潮市での事故を契機に、点検などの在り方が大きく改正になることも考えられる▼特にも公共事業に携わる側にとって、さまざまな公共施設の長寿命化対策が叫ばれて久しいものの、なかなか進展しないとの思いでいる人もいるだろう。予期せぬ事故に留まらず、防災面でも国土強靱化などに向けて老朽化対策を欠かすことはできず、年を追うごとに重要性は増していく。
- ●つむじ風 3月21日
- 県建設業協会(向井田岳会長)は、東日本大震災の教訓を踏まえて設定した3月11日「防災の日」に合わせ、広域的な災害を想定した情報伝達訓練を毎年実施している。今年度の訓練も先日行われ、本部・支部の情報連絡体制を強化した▼本部職員らは訓練終了後、個々の反省点などを洗い出した。情報連絡を担当した職員からは「情報を正しく伝えることが難しかった。自分で書き残したメモの内容を本部職員で一度確認した上で、支部に伝えた方がよかったと感じた」「土地勘の有無によって、情報の伝え方も変わる。柔軟な対応が重要」との声が聞かれた▼今後の備えに関しては、「資機材の搬入先をあらかじめリスト化し、候補地をある程度絞っておけば、情報の混乱を防げるのではないか」との提案もあった。向井田会長、菊池満専務理事兼事務局長らは、課題を洗い出し、次につなげていくことの重要性を職員と共有していた▼行政機関では人事異動の時期を迎える。新年度に入ってからも、協会本部・各支部や関係機関との連携の重要性を改めて確認したい。
- ●つむじ風 3月19日
- 北上公共職業安定所が主催する企業研究会&先輩就職者交流会が先日、県立黒沢尻工業高校2年生135人を対象に開かれた。土木科や電気科には、先輩社員らが訪れ、体験談などを通し地域企業や職業に対する理解を深めた様子だった▼交流会は、事業所の担当者による説明や先輩就職者の体験談などを通じて、地域企業や職業に対する理解を一層深め、新規高校卒業予定者の地元就職の促進につなげようと開いている。土木科には、3年前と10年以上前の卒業生が訪れた▼後日、土木科の先生と話す機会があり、先輩社員のことを聞くと、10年以上前でも面影があるとのこと。3年前の卒業生については、「格段にコミュニケーション力が上がり、成長を感じた」と目を細めて話す姿が印象に残っている▼同校は1日に卒業式が行われた。以前、土木科に在籍していた先生から4行ほどの祝電が届いていた。その中に「土木は家族」との言葉があり、深い言葉だなと感じた。卒業生が新たな環境で活躍することを願うとともに、取材することが密かな楽しみとなっている。
- ●つむじ風 3月18日
- 大船渡市赤崎町で発生した山林火災。9日に鎮圧を宣言した市は、14日から公的支援を受けるために必要な罹災証明書の交付を開始した。暮らしの再建に向けた対応は、徐々に次の段階に移りつつある▼13日に現地の県道を車で走ったが、沿道からでも分かるほど広範囲で斜面の山肌が一面薄黒くなっているのが見て取れ、立木は根元が焦げていた。立木が先端まで炭のようになっている区域もあり、山火事のすさまじさを感じさせる光景だった。山沿いでは焼け落ちた家屋も。現場では一部で復旧作業が進められていたほか、被害の状況を調査する関係者の姿も見られた▼他県からも含めいまだ多くの消防車が走っており、三陸町綾里では車両同士が擦れ違いで四苦八苦している場面にも遭遇。火災エリアに入る前には検問もあり、現地では「火」と「人」への警戒が続けられていた▼19日には応急仮設住宅の建設が始まる。整備戸数は40戸で、5月の完成が予定されている。本格的な再建はこれから。被災者に寄り添いながら着実に復興への歩みが進むことを願いたい。
- ●つむじ風 3月17日
- 県の人事異動が14日付で内示になるなど、3月末にかけて異動の時期に入ってくる。異動に伴う引っ越しも繁忙期で、国交省では引っ越し時期の分散に協力を呼び掛けている▼近年、人手不足などで希望日にあう引っ越し事業者が見つからない事態となっているとされる。今シーズンは「物流業界の2024年問題」も相まって、事態の深刻化が懸念される。分散化の実現には課題が山積しているだろうが、少しでも取り組みが進むことが期待される▼短い期間に物事が集中することで、さまざまな障壁が生じる。近年の天候を見ても、水不足になるほど雨が降らなかったかと思えば、過去に経験したことがない程の豪雨となり、災害に見舞われている。今冬も、日本海側を中心に災害級の大雪になった▼1月下旬から2月にかけて、国や県などから多くの工事案件が公告された。債務負担行為の設定などにより年度末の発注が増えた側面もあるもので、閑散期とされる年度当初からの工事着手を可能とするものだが、月ごとにムラのない発注件数となることが、真に求められる。
- ●つむじ風 3月14日
- 大船渡市の林野火災は9日に大船渡市が鎮圧を宣言し、10日には市の全地区で避難指示解除が解除された。本紙12日付1面では県建設業協会大船渡支部の須賀芳也支部長が、地域住民の暮らしの再建に向けた思いを語っている▼故宮城政章氏から、83年の久慈大火に対応した際の話を聞かせてもらったことがある。消防車のバックアップに生コン車で水を運んだこと、海に逃げ込んだ人を会社の船が救助したこと…。最後の一言はしっかり覚えている。「もらったのは表彰状1枚だけ。でも地域住民の命を救うことができた経験こそが、何にも代えられない財産になった」▼県建設業協会の向井田岳会長は以前、本紙の取材に対して、大規模災害に向き合う地域建設業の姿を以下のように表現した。「目の前の風景に呆然としながらも、その場でなすべきことを黙々と遂行する、そのこと自体が建設業の力だ」▼災害時などに地域建設業を動かすものは目の前の損得勘定だけではない。しかしそれにも限界がある。ちなみにここで言う「限界」とは、お金だけではないですよ。
- ●つむじ風 3月13日
- 東日本大震災から14年が過ぎ、もうすぐ新年度の春を迎える。東北や県民の一人として、3月11日を決して忘れることなく、三陸沿岸地域や岩手に目を向けていきたい▼震災後、建設行政や建設業界が総力を結集し、各地の復旧・復興事業に当たってきた。地域の安全な暮らしを一刻も早く確保するため、数々の建設現場が目の前で動き出していったことを今も思い出す。当時、工事現場の安全パトロールの際に、参加者に対し津波避難経路が事前に伝えられるなど、同時並行での取り組みも数多くあった▼行政、民間を問わず、4月には新しい職員や社員が入り、新入社員教育や各種研修の場などが設けられることだろう。もしかしたら、復旧・復興の現場で活躍した人たちの背中を見て、入庁・入職する若者もいるかもしれない▼震災後の課題をどのように克服したのかなども含め、復旧・復興で発揮した技術やノウハウなどを、若い世代に伝える取り組みも大切にしたい。ひいては、それが岩手の教訓の伝承、地域防災力の強化につながっていくと思っている。
- ●つむじ風 3月12日
- 凌風丸と啓風丸。気象庁に所属する海洋気象観測船で、海洋の表面から深層に至るまでの水温、塩分、溶存酸素量、海潮流などの海洋観測のほか、海水中や大気中の二酸化炭素濃度の観測などを行っている▼両船の観測データを解析した結果、日本南方海域と親潮域の海水中に溶けている酸素の量(溶存酸素量)が、世界と同程度かそれ以上の速さで長期的に減少(貧酸素化)していることが分かった。貧酸素化は、地球温暖化の進行による長期的な海水温の上昇に伴い発生すると考えられているという▼数値で見ると、海面から深度1000㍍までの溶存酸素量は、日本南方海域で10年当たり0・5~0・6%低下、親潮域では10年当たり2・5%低下している。溶存酸素量の減少は、地球温暖化の進行による長期的な海水温の上昇に伴い発生すると考えられている▼詳細は、気象庁ホームページの海洋の健康診断表で公開中だが、臨時診断として「24年の日本近海の年平均海面水温が過去最高を更新」とのトピックスも掲載されている。自分事として捉えなければならない。
- ●つむじ風 3月11日
- 東日本大震災の発災からきょうで14年を迎えた。弊社にも当時、小学生だった新人が昨年入社。今回の震災特集を担うまでになっており、改めて年月の経過を感じる▼以前、釜石市で取材した「ぼうさいこくたい2021」では、地元高校生が「私たちは震災の経験を伝えられる最後の世代」とし、「自分の経験や防災教育で学んだ知識を後世に伝えていきます」と力強く誓っていた。震災を経験していない世代が増えている中でも、伝え方を工夫しつつ地域の防災文化の醸成を図っていく必要がある▼宮古市は旧田老総合事務所の跡地に市災害資料伝承館を整備しており、6月の開館を予定している。規模は鉄骨造平屋建ての床面積462・04平方㍍。施設では津波、台風などの災害の歴史をテーマに、教訓を伝える資料が展示される計画となっている▼山本正德宮古市長は「伝承館で歴史を学んでもらい『災害は必ず起きる』という意識を共有したい」と語っていた。震災の記憶の風化が懸念されている今、防災教育をさらに充実させ次の災害に備えていきたい。
- ●つむじ風 3月8日
- 東日本大震災の発災から14年を目前に、おのおのさまざまな思いを巡らせているに違いない。自然災害の脅威に毎年のように苛まれ、地震や津波、豪雨の恐ろしさを感じずにはいられないが、特にも今年に入ってからは、山林火災の怖さについても改めて思い知らされている▼1月には、アメリカのロサンゼルス近郊で大規模な山火事が発生した。本県でも、気仙地区や宮古で山林火災が相次ぎ、特にも先月26日に出火した大船渡市での山林火災は、規模の大きな被害となっている。被災者が一日も早く元の生活を取り戻すことが願われる▼相次ぐ山林火災に、1961年に発生した三陸フェーン大火などを思い起こした読者もいたのではないか。同大火では、本県下14カ所から発火し、推定焼失面積は約2万6000㌶に及ぶともされる▼各種災害の発災から月日を重ねるにつれ、記憶の伝承の重要性は増していく。経験は「あの災害でも大丈夫だったから今回も大丈夫」と考えてしまう危険性もはらむが、先人からの教えや取り組みを大切にして、有事に備えたい。
- ●つむじ風 3月7日
- 岩手労働局は、県内建設業一斉監督指導の実施結果を公表した。監督を行った135現場のうち、何らかの労働安全衛生法違反が認められた現場の数は69現場。違反率は51・1%だった。直近5年間では20年の48・8%に次ぐ低い数字であり、3年連続で違反率が低下している▼違反の内容を見ると、最も多かったのは「墜落防止措置」で違反率は71・0%。違反内容の中でも突出しており、過去5年間の20~30%台と比較しても、24年は飛び抜けて多いと言わざるを得ない▼24年の建設業における労働災害(速報値)を見ると、「墜落・転落」によるものが56人と最多で、全体の30・1%を占める。例年「墜落・転落」による労働災害の割合は3割強で、岩手労働局の第14次労働災害防止計画では、墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントへの取り組みをアウトプット指標に設定している▼近年は高所での対策が進んだ反動か、脚立や重機など比較的低い場所からの墜落・転落が増えているとのこと。労災防止に特効薬はない。まずは基本的な対策の徹底から。
- ●つむじ風 3月6日
- 県建設業協会(向井田岳会長)は、東日本大震災の教訓を踏まえ、3月11日を「防災の日」と定めている。毎年、11日の前後に広域的な災害を想定した情報伝達訓練を実施しており、今年度の訓練は10日に行われる予定だ▼今回も、一部の内容を事前には公開しないブラインド方式を取り入れ、訓練に臨むこととしている。昨年度の訓練で初めて導入した方式で、参加者からは「緊張感を持って訓練できた」との声が聞かれた▼前回の訓練では、実際に機器が繋がらないという事態に見舞われたが、情報共有の手段を切り替えるなど、協会本部・支部とも臨機応変に対応していたことを思い出す。訓練後の意見交換においては、「支部会館が市のハザードマップで、高さ3~5㍍の浸水想定区域に含まれている」などの課題も挙げられていた▼今年度の訓練でも、新たな課題や貴重な情報を発見できるかもしれない。「防災の日」の訓練は、県土の強靱化につながる取り組み。それぞれの地域の守り手が持っている「地元を見つめる目」を共有し、教訓をつないでいきたい。
- ●つむじ風 3月5日
- 昨年6月から9月に国土交通省と各都道府県は、小中学生を対象に土砂災害やその防止について理解と関心を深めてもらおうと絵画・作文を募集。入賞作品が決まった▼全国から絵画の部の小学生が1205点、中学生が1415点、作文の部の小学生が376点、中学生が661点の合計3657点の作品が寄せられた。審査会で選考し、国土交通大臣賞4点、国土交通事務次官賞60点が決まり、盛岡市内の中学生の作品が事務次官賞に選ばれた▼表題は「土砂災害を防ぐために」。その中で、県内で伝えられている「命てんでんこ」を挙げ、判断の大事さを強調。土砂災害の種類も紹介し、「それぞれの土砂災害に逃げ方があるので、その時の判断が大事」とし、さらに災害時の本物と嘘の情報を見分けて判断することの大事さも訴えている▼自宅や現場であれば、ある程度の判断を下すことができるだろう。いつどこで何が起きるか分からない時代。土砂災害の前兆現象を確認しつつも、いつもと違う何かを感じる五感を養いながら、一人ひとりの防災意識を高めたい。
- ●つむじ風 3月4日
- 2月26日に大船渡市の赤崎町字合足で発生した山林火災。焼失面積は3日午前6時時点で約2100㌶まで拡大し、延焼が続いている。現場では、全国から派遣された緊急消防援助隊の応援を受け消火活動が展開されており、今は早期の鎮火を願うばかりだ▼「合足でまた山火事が発生した」との一報を同市隣の住田町で聞いたのは26日の午後2時。沿岸部は強い風が吹いていたため「燃え広がらなければよいが」と危ぐしていたが、まさかここまでの事態になるとは。山林火災の恐ろしさ、消火の難しさを思い知らされる▼本県沿岸地域では、山沿いの急傾斜地に建てられている住居を目にすることも多い。加えて、震災復興の防災集団移転促進事業では、高台山間部を切り開くなどして住宅団地を整備していることから、周囲が山林に囲まれている場所も増えており、山火事には十分な注意が必要になっている▼県山火事防止対策推進協議会は5月末までの期間で、「山火事警戒宣言」を発令している。空気が乾燥し風も強い時期だけに、防火管理の徹底を心掛けたい。
- ●つむじ風 3月3日
- 「制度化されたころは、どこかに行く時のルート上にあることから立ち寄る場所だったが、今ではその場所へ行く目的化が定着した」と道の駅について話すのは、佐藤善仁一関市長。道の駅「だいとう」の登録証交付の際に述べた▼道の駅は、1月31日の第62回登録で全国1230駅となり、同日に9駅登録。県内では、一関市大東町の「だいとう」のほか、盛岡市の「もりおか渋民」と山田町の「ふなこし」の3駅が登録され39駅となった▼道の駅では、第3ステージに位置付け、「地方創生・観光を加速する拠点」と「ネットワーク化で活力ある地域デザインにも貢献」に向けた取り組みも進む。その一環で、都道府県の地域防災計画等で、広域的な防災拠点に位置付けられている道の駅を防災道の駅に選定している▼道の駅「だいとう」は、奥州市と陸前高田市を結ぶ国道343号の中間点に位置することなどから、防災道の駅への登録も目指している。防災道の駅に、県内では遠野市の「遠野風の丘」が選定されており、道の駅に期待される役割は大きくなっている。
- ●つむじ風 2月28日
- 本紙8面に、月2回ペースで「いわて防災学教室」を掲載している。岩手大学地域防災研究センターに所属する教員を中心に、地震、火山、砂防、地質、水工学、防災教育など幅広いテーマで執筆いただいている。連載開始は15年7月。一度お休みをはさんで18年6月に再スタートし、今月26日付で再開から100回を迎えた▼この連載が目指すのは、地域の守り手である建設産業界が災害に強い地域づくりへの意識を高め、防災に対する知見を深めること。連載を再開した18年は県の復興計画期間の最終年に当たり、同時に台風10号災害からの復旧工事が本格化した年。加えて南海トラフ地震や北海道沖の超巨大地震などのリスクが話題になっていた時期でもあった。幸いにも行政やコンサル関係者からご好評いただいている。ありがとうございます▼すっかり手前みその宣伝みたいになってしまったが、読者の皆さんが改めて防災への関心を高めるきっかけになれば幸いです。まもなく東日本大震災の発生から14年。本紙を捨てずに読み直してくれるとうれしいです。
- ●つむじ風 2月27日
- 埼玉県内で発生した道路陥没事故と、水道管の破裂・漏水による被害。連日、テレビや新聞、SNSなど、さまざまな媒体で話題に挙げられている。多くの皆さんにとって、生活に直結するインフラの重要性を見直す一つのきっかけとなっているのだろう▼本県においても、インフラの機能の維持は重要な課題だ。例えば公共土木施設と一言でいっても、道路や河川、ダム、砂防、上下水道、港湾など、多岐にわたる。農林水産分野のインフラにも目を向けると、農道や林道、漁港施設などがある。どれも県民の暮らし、なりわいを支える岩手の財産だ▼建設業は、県民の生活や地場産業などを下支えする基幹産業。施設の管理主体の行政と建設業界が一体となって、広大な県土のインフラを守っている▼施設の老朽化を踏まえ、身の回りのインフラに関する一般市民からの注目度も一段と高まりそうだ。建設業は、ものづくり産業と言われる。インフラの整備などを通じて、地域に貢献する「人づくり」に汗を流していることも、多くの人に知ってもらいたい。
- ●つむじ風 2月26日
- 激甚化・頻発化する水害から国民の生命と暮らしを守るための新たな水害対策として、流域全体で治水対策に取り組む「流域治水」。官のみならず企業や団体などあらゆる関係者との連携が重要となっている▼国土交通省は、流域治水に取り組む・支援する企業等を流域治水オフィシャルサポーターとして認定しており、25年度の認定に向けた募集を始めた。すでに県内企業も認定され、流域治水に関する情報をウェブページやSNSで情報発信するなどの取り組みを行っている▼サポーターの条件として、企業等のウェブサイトやSNS、広報誌、ポスターへの情報掲載をはじめ各種イベント、セミナー、学会、講座、研修などでの紹介。貯留施設の設置など治水対策に資する取り組みの実施、防災活動への積極的な参加―などを挙げている▼ある企業では、流域治水のポスターや広報資料を社員が社内外や取引先などにも伝えることで、水害予防に対する理解を広めているという。流域治水を考えるきっかけを作りながら、流域全体の総合力で安全・安心を実現したい。
- ●つむじ風 2月25日
- 20年に宮古工高と宮古商高、24年に福岡工高と一戸高が統合。25年には久慈工高と久慈東高の統合が予定されるほか、水沢工高と一関工高の統合も将来的に計画される。工業高校を巡る環境が大きく変化している▼各工高の学科数も減り、建設業の担い手確保にも与える影響は大きい。人口減少下での統合には、やむを得ない面もあるのかもしれないが、専門校の特長を考慮した統合を願う業界関係者も多いことだろう▼専門校が地元からなくなったことを受け、地元から他地区の専門校へ通学できるよう、アクセス性を良くする施策を求める声も聞かれる。専門校の持つ魅力のPRなども合わせた施策が望まれる▼来月5、6日には県内県立高校の入試が予定されている。地域差などもあるが、志願倍率では、普通校などに比べて倍率が低く厳しい状況の専門校が多く見受けられる。県内の高校入試では、今年度から推薦入試に代わって特色入試が採用されるが、取り組みの趣旨とされる志願倍率の低下等への対応、各高校の魅力化や特色化の推進につながってほしい。
- ●つむじ風 2月21日
- 県は建設関連業務における簡易総合評価落札方式の見直しを行う。4月1日以降に公告する業務からの適用。総合評価の対象を現行の「500万円以上」から「1000万円以上」に引き上げるとともに、簡易な業務は設計金額にかかわらず価格競争とする▼この変更は、建設関連業務における受注の偏在を解消することを目指すもの。業界団体からも見直しを求める声が上がっており、県では今回の措置を通じて、県内企業の受注機会拡大を目指す考え▼建設関連業務で条件付一般競争入札と失格基準価格の試行がスタートしたのは08年度。前年度は全体の1割近くが落札率50%を下回り、10~20%台という極端な低価格での受注もあったようだ▼以降は条件付一般競争の全面実施、失格基準の見直しなどを行いながら、簡易総合評価落札方式は12年度のスタート。極端なダンピングはなくなり、業務成績が受注に反映されるようになった。それでも当初は想定していなかった課題も出てくる。入札制度に完成はない。必要な見直しは、迷わずスピード感を持って。
- ●つむじ風 2月20日
- 例年、この時期は、県内14市の新年度予算案が発表される。記者会見の場が設けられた際には、新年度のまちづくりに向けた市長の思いを聞くことが出来る▼最近の例を挙げると、久慈市の記者会見では、遠藤譲一市長が地域活力の創出へ、「予算の数字としては表れていないが、浮体式洋上風力発電の取り組みは一定の準備段階にあり、来年度はもう一段ステップを進めたい。久慈港の基地港化にも力を入れていく」と展望。滝沢市の会見では、武田哲市長が「滝沢市は県北振興の入り口の役割も大きいと考えている。周辺市町村と連携し、方向性を確認しながら県北振興の取り組みを進めていきたい」と語った▼県の構想路線に位置付けられた(仮称)久慈内陸道路の早期実現なども、将来の県北振興を見据えた代表的な取り組みと言える。県北地域は畜産業や漁業をはじめ、農林水産分野でも強みを持っている。新年度も引き続き、県北地域の強みを引き出す事業展開を期待したい。地域や地場産業の振興のためには、基盤をなすインフラ、建設業界の存在が大きい。
- ●つむじ風 2月19日
- 高校で必修の「総合的な探求の時間」。専修大学北上高校は、その時間を専探(SENTAN)と称している。現在、北上市とコラボし北上駅から同校まで「歩きたくなる道とは?(通称・ウォーカブルゼミ)」に取り組んでいる▼北上市は、都市拠点の形成に向け市中心部の再整備を計画。北上駅鍛冶町線を「まちなかの背骨」と位置付け、居心地が良く歩きたくなる道路の整備を検討中だ。ウォーカブル化を図ることで整備効果を点だけでなく面的な波及にも期待を寄せている▼先日の市景観フォーラムで、ゼミの取り組みが紹介された。同路線の白地図に書き込まれた彩り豊かな空間活用のアイデアには、ウォーカブルという問いを自分事として捉え、その問いから学びを深めている様子が感じられた▼フォーラムでは、高校生を交え3~5人がグループとなり話し合った。各グループからの提案を見ると、ウォーカブルのキーワードの一つは「居場所」だろうか。いろいろな声を聞き、問いを深め、どのような未知(道)の答えが導き出されるのか楽しみだ。
- ●つむじ風 2月18日
- 宮古市内では、わさびの加工を手掛けるカネ弥㈱(釜石市)が、同市臨港通の既存建物を活用し、新工場の立地を計画。4月の操業を目指し準備を進めている▼立地場所は、同市臨港通403番1ほか。工場では、わさびの1次加工に加え、わさび製品の製造を開始するほか、新たに地元水産物・アカモクを使った製品の製造も予定している。宮古市では33社目の誘致企業で、製造業としては2013年1月以来、12年ぶりの新規立地。県産わさびとアカモクの消費拡大、地域の雇用拡大に期待が寄せられている▼以前、沿岸部に立地した畜産関連企業を取材した際、企業側は立地を決めた要因として、「三陸沿岸道路が整備されたことも判断する上でかなり大きかった」と語っていた。円滑な物流を支える幹線道路は、企業立地の重要な判断材料になっている▼県内では、沿線自治体から三陸沿岸道路の交通環境の充実や、横軸幹線のさらなる整備が要望されている。地域の産業振興を後押しするためにも、道路ネットワークの整備促進と機能強化が求められるだろう。